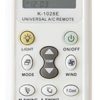なぜ昆布は、海の中でダシが出尽くしてしまわないのでしょうか?
「真水だからダシが出る!ので塩水ではダシは出ない!」
違います。
「海水は塩分濃度が昆布本体より濃いから出汁がでない!」
これは、浸透圧のことですね、ナメクジに塩をかけたら小さく縮む原理ですがこれも違います。
「昆布は熱湯で出汁を取るので、冷たい海ではダシは出ない!」
合っている部分もありますが・・・ちょっと違います。
ちょっと待ってください!
そもそも、そんな疑問を持たない人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。
答え
昆布から取れるダシはアミノ酸の一種でグルタミン酸。
グルタミン酸=ダシ
グルタミン酸が、うま味調味料の主成分となります。
疑問を言い換えるとこうなります。
なぜ海の中で生えている昆布のグルタミン酸が海水に溶け出さないのだろうか。
それもそのはず、昆布が生きている間はグルタミン酸というのは表皮細胞に蓄えられています。
昆布の表面では生きていくために必要なものを細胞に取り入れ、不要なものを排出する選択透過性という機能が働き、グルタミン酸は必要なものとして外には出ないようになっています。
ただこの機能にはエネルギーが必要ですので、生きている間にしか機能しません。
なので、昆布が死んでしまうとグルタミン酸(ダシ)は出るわけです。
昆布だけではない
これは昆布だけに備わった機能というわけではありません。
この機能が無ければ、海で泳いでいる魚は最初から塩漬け状態になってしまう。
うま味どころか全部が海水の味になってしまいます。
そうなったとしたら、海水がダシの利いた味になることでしょう。
この機能は魚や海草だけでなく、あらゆる動植物に備わっている機能で人間も同じ。
結論
昆布が海でダシがでないのは、昆布が海の中で生きているからです。
豆知識
だし昆布をつくる工程で、昆布を海から収穫して海岸で乾燥します。
すると、この細胞のしくみがなくなるとともに、うまみ成分(グルタミン酸)が昆布の中に濃縮していきます。
だから、乾燥しただし昆布からはおいしいダシがとれるのです。
ダシは水よりもお湯の方が、より旨み(アミノ酸等)が溶け出しやすいので煮出してダシを取ります。
海の中であっても死んでしまうと細胞膜がこわれ、成分が流れ出てしまいます。
これは水温が低くても起こり、生きている状態でも高温に晒すことで同様な流出(ダシが出る)は起こります。