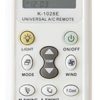請負(うけおい)とは、受託(じゅたく)に含まれるものなのですが、契約の内容が違います。
当社で受託している業務の中でも、請負業務と受託業務が混在しています。
実は、当社で働いている人間の中にも、その違いを誤解している人もいます。
プロである以上、ここは明確に知っておく必要がありますので記事にしておきます。
受託とは
受託とは、頼まれて業務を引き受けること。
また、委託(いたく)を受けること。
たまに、仕事を受ける当事者が個人の場合は、請負契約にはならないなんて話を聞くこともありますが、当事者が法人であろうと個人であろうと、何の関係もありません。
請負業務になるかどうかは、契約の内容のみによって決まります。
委託とは
委託とは、一定成果を出すことを義務としない行為の実行を、人に頼んで代りにしてもらうこと。
委託には、法律行為の委託と、法律行為以外の委託があります。
一般的に「委任」と言うと、法律行為の委託を意味しています。(民法第643条)。
法律行為以外の事務の委託を「準委任」と言います。(民法第656条)。
準委任は、法律行為以外の”事務の”委託となっていますが、これは広く拡大解釈することができ「法律行為以外の業務の遂行」と理解することができます。
例えば、ビルの管理やシステムのメンテナンスなども準委託に該当します。
準委任の報酬は、月幾らだとか、1件毎に幾らなどと決まることがほとんど。
請負とは
受託契約の内容が「仕事の完成」となっている場合、これは請負業務となります。
請負業務の参考例
委託者からガス給湯器の交換工事を、幾らの報酬額で、何時迄に完了させてください。
工事内容や交換後のガス給湯器に瑕疵がなければ、工事完了後に契約時に約束した報酬を支払います。
この工事に人工(にんく)を何人使うか、材料をどこから調達するかなど、委託者からは一先関与を受けません。
その代わり、すべての責任は、受託者が背負うことになる契約が請負業務となります。(民法632)
委託者と受託者の関係
委託者の場合
どの受託者に依頼するかを選択することができる。
受託者の体調管理などの労務管理義務がない。
受託者の場合
受託者は委託を受けるか拒否するかを選択することができる。
もちろん、心情的な部分もあるため、お互いが譲り合って話し合いをするのが現実。
一見、委託者の立場の方が有利に見えるのですが、受託者がいなければ、委託者の業務は破綻します。
繁忙期になれば、委託者は依頼する業務に追われ、受託者は休む暇もなくなります。
そして委託者は、受託者を探すのに必死になっているのですが、そんな時に受託者から「休みたいから…」と言われても心情的には納得しにくいことは確か。
受託者は、休むといったことも業務として捉える必要があり、休暇業務を別の業務と言い換えて、スケジュール管理する必要があります。
間違えても、委託者に「休日が欲しいからその業務は受けられない」なんて事は言わない方がお互いのためでしょう。
さいごに
委託者は、サラリーマンであるケースが多くなり、受託者は個人事業者だったり、法人だったりします。
サラリーマンは、人間として扱われますが、事業者に要求されるのは請負の場合、「仕事の完成」しかないことを理解しなければいけません。
この温度差により、委託者と受託者が衝突することがよくあるのですが、今一度、自分たちの立場を考え直してみると、意外にスムーズに仕事がこなせるようになるのかもしれません。