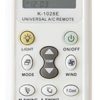イオン化傾向
イオン化傾向は中学の理科で習うのですが、習っていない人や忘れてしまった人のために説明しておきます。
そんなに難しくはありませんので安心してください。
水の中で金属が金属結合から金属イオンとして出やすい順に並べたものをいいます。
つまり、イオンになりやすい順番に並べたものと考えてください。
これがイオン化傾向。
K(カリウム)←Ca(カルシウム)←Na(ナトリウム)←Mg(マグネシウム)←Al(アルミニウム)←Zn(亜鉛)←Fe(鉄)←Ni(ニッケル)←Sn(スズ)←Pb(鉛)←H(水素)←Cu(銅)←Hg(水銀)←Ag(銀)←Pt(白金)←Au(金)
確か覚え方はこうでしたね。
「貸(K)そうか(Ca)な(Na)、ま(Mg)あ(Al)当(Zn)て(Fe)に(Ni)す(Sn)な(Pb)。ひ(H)ど(Cu)す(Hg)ぎ(Ag)る借(Pt)金(Au)」
まぁ白金のところだけは全く意味が分かりませんが確かこんな感じでした。
イオン化って何
平たく言うと腐食するとか錆びるとかするってこと。
これを詳しく説明すると本題から大きく外れてしまいますので簡単に説明します。
イオン化とは、物理学の分野では荷電(かでん)と言い、化学の分野では解離(かいり)と言います。
分子や原子といった、その材質の一番小さな塊の単位で熱や電磁波などの影響を受けると電子を放出しり得たりすることを言います。
化学で説明すると、電解質(塩)が溶液中や融解時に陽イオンと陰イオンに分かれることを言います。
卑金属と貴金属
通常の空気には多少の水分が含まれているものです。
水素(H)よりもイオン化傾向が下(イオンになりやすい)の金属は、空気中の水分でイオン化します。
そして、空気中の酸素と結びついて酸化する金属となり、これらを卑金属(ひきんぞく)と言います。
酸化とは錆びることを意味します。
私はこれらを「いやな(卑)金属)と呼んでいます。
水素(H)よりもイオン化傾向が上(イオンになりにくい)の金属は「とうとい(貴)金属」と呼ばれ「貴金属」といいます。
卑(いやな)金属は単体でもイオン化して錆びようとしますが、イオン化の違う金属を接触させた場合、イオン化の下位の金属はさらにイオン化が促進されるのです。
銅に関しては水素よりも上なので通常は卑金属に分類されます。
しかし、場合によっては貴金属に分類されることもあります。
電極電位の数値を見ると、銅は確実に貴金属に分類されそう
電極電位
リチウム (Li) -3.04
カリウム (K) -2.93
カルシウム (Ca) -2.76
ナトリウム (Na) -2.71
マグネシウム (Mg) -1.55
アルミニウム (Al) -1.662
マンガン (Mn) -1.185
亜鉛 (Zn) -0.762
クロム (Cr) -0.744
鉄 (Fe) -0.447
カドミウム (Cd) -0.403
コバルト (Co) -0.28
ニッケル (Ni) -0.257
すず (Sn) -0.138
鉛 (Pb) -0.1262
水素 (H) 0.00
銅 (Cu )+0.342
水銀 (Hg) +0.851
銀 (Ag)+0.800
白金 (Pt)+1.118
金 (Au)+1.498
違う金属を接触した事例
流し台にくぎ
ステンレスの流し台の上に鉄くぎを置いて一晩でも置いておくと、次の日には鉄くぎが真っ赤に錆びてしまっていることがあります。
ステンレスは合金ですからイオン化列には見当たりませんが、イオン化列に当てはめると銅(Cu)と同じくらいの位置になります。
道理でステンレスが錆びにくいわけです。
この場合、鉄くぎはステンレスよりもイオン化傾向が下となりますので、鉄くぎ側のイオン化(腐食)がステンレスに接触することにより促進されたことになります。
鉄の建材にステンレスのボルト
鉄の建材にステンレスのボルトで固定した場合、建材側の鉄が腐食することになります。
ステンレスを使えば安全と思って選択しても、結果的に母材である建材の方を腐食させることになり被害が大きくなります。
この場合は、同じ鉄のボルトで固定するのが望ましい選択と言えます。
しかし、どうしても異種金属を接触させる必要がある場合は、直接接触しないように「絶縁」させて使用するようにします。
乾電池はこのしくみを利用している
イオン化傾向(電位)の違う二つの金属が電解質中で接触すると卑金属がアノード(-)となってイオン化(腐食)が助長され、貴金属の方はカソード(+)となってイオン化が抑制されます。
アノードとは、負極なのでマイナスで、カソードとは正極なのでプラスとなります。
乾電池には1.5ボルトとか3ボルトとか、いろんな種類があります。
これは電位差と言うのですが、金属は水素を基準として、それぞれが固有の電位を持っています。
イオン化傾向は、この電位の低い順に並べたものと言い換えることが出来ますので、電位が大きく離れている金属同士の電気が流れやすい状況(電解質中)で接触するとイオン化が大きくなります。
これを「異種金属接触腐食」といい、使用する金属によって1.5ボルトとか3ボルトとか電圧が変化するのです。
自由研究に使うなら
身近にある金属を利用して、たくさん電池を作ることが出来ます。
炭とアルミのようにありふれた(すでに多くの方が実験している)ものでは入賞することは出来ません。
そして、それらの電池がどれだけの電圧になったのかを記録するといいでしょう。
イオン化傾向をみれば、どの組み合わせにすると電圧が大きくなるのか予想が付きますが予想通りになるのかどうかを確認してみましょう。
そして、予想と違う場合それはなぜなのかを追求してみましょう。
電解質は変化させないようにすることが望ましいです。
電池の容量や電流については追及しないで良いと思います。
意外なもので電池を作って見てはいかがでしょうか?
例えば、レモンなどの食べ物とかでも出来ますよ。
まとめ
街を歩いていて、ふと建材を見てみるとステンレスの建材にアルミリベットで固定しているものとかを目にすることがあります。
どちらも錆びにくいからと思って選択しているのかもしれませんが、雨などの水に触れるとアルミリベットが腐食していきます。
そのうちボキッっと折れることになると思うと怖いなぁって思うことがあります。
プロの施工でも、このような初歩的なミスをすることがあります。
自転車や家電でも、ねじが錆びているからって鉄のねじからステンレスのねじに変える人が居ますが絶対にやめたほうがいいですよ。
基本は違う金属を接触させない事です。
例外として、ステンレスのボルトにステンレスのナットを締めるなど、ステンレス同士の場合は焼きつきを起こして締めた瞬間に一生ナットが緩まないようになることがあります。
ステンレス同士の組み付けには、焼き付き防止のケミカルを使用する必要があります。
できれば避けたほうがいい組み合わせです。